1
「作文と教育」編集部のK氏から、ぼくは、作文を書くように言われた。題は、「京浜地帯の子ども−−その生活指導と生活綴方」というのだ。
課題されたぼくの上に変化がおこった。
2
その一つは、“おこらなくなった”ということだ。とくに、作文の時間などには、以前ほどおこれなくなった、ということだ。
「お前、何も書くことないのか! うれしかったことも、食いたかったことも、くやしかったことも、なんにもないのか!」
「お前は、よっぱらいみたいに、ボヤーッとしてるからだよ!」
「ちょっと見せろ! なあに?! ええと、一、二、三、四…………
なあんだ、たったの37字か、たったのこれだけでおしまいか。おったんちんの、えんぴつケチンボヤロー!」
なんて、いえなくなった。それどころか、
「ご苦労さま、年はもいかぬ三年生よ。こんな大変なことやらせて申しわけない。ヒデキよ。お前は、さっきから、題と名前書いただけで、申しわけなさそうな顔してるが、そうキョウシュクした顔しなくていいのだ。お前がしてる勉強は、とってもむずかしいことなんだから。」
といった、思いやりのある顔して、教室の中を静かに歩く先生になった。
3
なぜか? K氏から、
「書きなさい。」
といわれて、題と名前を書いた。しかし、それから先へ、ちっとも進まないからだ。書けないから、ねちゃった。つぎの朝、登校の電車の中で考えた。書きだしは? 中みは? 結びは? 頭の中には、日本の、京浜工業地帯の、生麦の学校で、九年もくらして来たのだもの、いろんなことがガサガサある。だけど、どう書いたらいいか、わからない。家へ帰ってまた考えた。書けない。ねちゃった。
4
そこで、ぼくは、考えさせられざるを得なくなった。
「ああ、綴方というものは、目の遠くなったおふくろが、糸をとおそうと、またやって、またやって、またやって、そしてまたやっても、なかなかとおらない、それと同じくらい、とてもとってもむずかしい仕事なんだなあ。」
「子どもが、えんぴつにぎったまま、うらめしそうな顔してるのは、むりのないことなのだなあ。」と。
5
それから、朝っぱらの用務員室で、つぎのような会話をするようになった。相手は、すじ金いりの職工さん上り。今は、学校の警備員をしている方。
「おはようございます。こないだの晩、キリンビールの裏の長屋へ行ったんだけどね、『今晩わ、学校のもんですが』って、いったらさ、おやじさんが『えーっ、なにーい!』って、すごいけんまくなのさ。
こっちも、こんなかっこうしてるし、人相悪いからだけどね。
でね、そのおじさん、耳が遠かったのさ。
たしかね、パイプ屋だとか言ったんだけどパイプ屋っていうの、耳遠くなるの?」
高橋さんは、エントツだらけの町に長年勤めてる先生ってのに、なんたらこったという顔で、教えてくれた。
「それはね、セイカン屋だよ、先生。」
「あ、そうか。そうそう、そういえば、そうだそうだ。セイカン工って、おれとおんなじぐらいの年で、もう耳遠くなっちゃうの。」
「そりゃ、そうですよ。鉄ぱんをひっぱたいて、ひん曲げたりするんだから。」
「ひん曲げてどうするの?」
「水のタンクや油のタンクつくるのさ。」
水のタンクも、油のタンクもわからなかったけれど、工場街の先生という名の手まえ、もうわかったという顔して、
「ああ、セイカンか。一つリコウになった。高橋さん、どうもありがと。」
とお礼をいって、話切りあげた。
6
なぜ、朝っぱらから、そんな質問したのか? K氏に出す作文には、工業地帯のにおいをこめたいものだ−−そう思ったからだ。
パイプ屋、セイカン屋、図面、タンク、などなどの名前をつぎ合わせて、一ぺんの作文をでっち上げることにより、さすが工業地帯の教師だけある、などと思ってもらいたい下心から出た質問だ。
なんてイヤなヤローだ。
横浜作文の会などで、よく言う。
「四年でも五年でも、六年だって、『お前んちのとうちゃん、どこの会社いってんのよ』と聞いても、会社の名さえ知らぬ子がいっぱいいる。こんなところに、町の子の問題があるんだなあ。
とうちゃん、どこで、どんな汗たらして、どのくらいよごれて、帰りふろへはいって、そうして、金持ってきてくれるのだ、ということ、何も知っちゃいないんだよ。いや、劣等感とか、差別感から知らそうとしないんだよ。問題はそこんとこにあるんだよ。」
などと、言う。このオレがだ。工員さんのこと知らねえ先生が、何ほざきやがるんだ。そんな教員が工員さんの子教えていることこそ問題なんだ−−といわれたって仕方ない。
7
課題作文のことなど、縁のなかったころのこのオレ。課題作文のことを考えるようになったこのオレ。その変り目の所に、ハッキリ浮き上がってきた小沢いさお。この、小沢いさおの正体というものは、大した反省材料になった。
〈ヒトツ〉
子どもの身になって、ひとりびとりの子どもをいとおしむような教師ではなかった。
〈フタツ〉
その子のランドセル、えんぴつなど、それがなくてはリコウになれぬという物。それを買ってくださるその金は、どんな仕事の中からもうけてくるのか、ということに、心よせる教師ではなかった。
けっきょく、このオレは、子どもを大切にしない、人間をソマツにする教師であった。
8
ぼくは、今まで、日本の教育界において、四十年の伝統に、サンとして光彩を放つ、生活綴方教育運動を受け継ぐ、光輝ある民族の教師、国民の教師のひとりである。と、自負していた。
「よくやるねえ、『エントツ』あいかわらずやってますねえ。よく続きますねえ。またスイセンになりましたね。『エントツ』何年めになります?」
「九年になりますよ。」
「ヘエ、ねえ……」
なんていう声をきくときなど、
「へへ、オレも、小西健二郎の、つぎのつぎのつぎの、そのまたつぎぐらいの位にははいるだろうな。」てなものだった。
そのオレも、このたびこそ、ウンもスンもなく、生活綴方サルまね教師であることを、つくづくわからされた。
9
その、「わからされた心」で、自分が、今までやってきたこと、今やってることを、考えてみた。
ポケットから紙きれを取り出して読んでみる。九月から受持った、三年生のハガキだ。
★ ぬくいひろし
先生、てっちゃんに、ぶってじしらなかたから、てっちゃんおせいてといたら、すぐおせいてくれました。てっちゃんて、ぼくすきだよ。てっちゃんてっちゃん。ぼくのすきなてっちゃん。ぼくほめてやるよ。先生。
これは、
「先生は、たのんだことなんか一ぺんもないのに、よく友だちのつげ口する人がいる。
そういう人がウンといる。だけど、友だちの良いこと話してくれる人はすくない。そういうえらい人は、どの組でも、ふたりか三人ぐらいしかいないものだ。
もし、みんなの中に、そういうえらい人がいたら先生に話しておくれ。ハガキや日記なんかに書いて、読ませておくれ。」
といったふうなおだてにのって、書いてくれたものだ。ぼくは、何年もっても、学年始めなかばを問わず、よく、こんなもの書かせている。だから、五・六年前の文集にも、
小林さん
高橋 洋佑
当番が終わって、
ぼくが
「良い子の紙」を
書いていると、
がらりと戸があいた。
小林さんが、
バケツをぶらぶらさせてきた。
小林さんは、
ああ、つかれたという顔だ。
ギュッとしぼったぞうきんが
バケツの中で
コロコロころがっている。
ハッキリしてる
田中英次郎
手は、
さかなが泳いでいるようだ。
本多君、
毎晩、米といだり、
ちゃわんをあらったりしている。
時には、
口をとんがらして、
ご飯をたいている。
「本多。ふろ行くべえ。」
と、頭を前に出していった。
「だめだってよ、これがないから。」
指を丸め、
ニヤニヤしながらいった。
働く本多君、
なければ「ない。」と、
ハッキリいう本多君。
といった詩がある。
こんな詩などが、ぼくの組から生まれているのは、生活綴方的教育方法に力こぶをいれてる教師たちが、口をひらけばいう、「人間を大切にする教育」に、まねたところからきている。まねはあくまでまねであった。
勤務評定があったのならともかく、そんなもののない学校なのに、おれは、「同僚教師の良いところをさがす」おおらかな教師とはうらはらの教師であった。三年生が、さも手がら顔して、
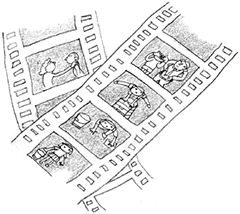 「○○はね、先生、まだ一ぺんも本よんだことなんかないんだよ。」なんて、つげ口するようなちょうしで、校長室へはいっていったようなことこそなかったものの、
「○○はね、先生、まだ一ぺんも本よんだことなんかないんだよ。」なんて、つげ口するようなちょうしで、校長室へはいっていったようなことこそなかったものの、
まるっきり話をしたことない子、ぼくの手におえなかった子が、その先生の組にはいって、ふた月もするかしないうちに、教室で手をあげるようになった−−なんて、けっこうな話をきいたとき、その子のために、おせきはんをたいても、まだたりないとき、そねみねたみ、心の中で、「チクショウ」と舌うちしたり、子どもたちの前で、
「おまえなんか、二年の時なにやってたのよ。こんなの二年の一学期にやる勉強だ。」
などと、二年の先生にあてこするようなことをいったり、親たちから、前の受持の悪口みたいなものを聞かされ、ちょっと口もとをほころばせそうにしたり、
などなどいっぱいあった。
だから、こういう教師のいる教室だから、「良い子の詩」なども生まれはすることがあったけれど、勉強のおくれた子をバカにするような空気はなかなかなくならなかったし、今のこのクラスだって、病気のお友だちのお見舞にいくような子は大変めずらしい。一里も二里もはなれている村の子ではないのに。「先生、家しらねえもん。」なんてすましている。学級委員のバッジつけてる子が……。
「人のつげ口などするな。そんなことより、人の良いところをさがせ!」というコトバはまず、このオレ自身に投げかけられねばならぬコトバであったわけなのだ。
10
そこで、綴方勉強をはじめて十一年め、ぼくの教室から出る「学級だより」としては、(ぼくにとって)カッキ的な、つぎのような記事がのるようになった。
号令一本ではダメ
−−高橋さんに学ぶ−−
三組が体育をやっている。今度は、マットの上を、くるくるころがって行くやつだ。
こまかい所に気がつくな、と、あらためて思う。山崎武久君のおかあさんが、
「女の先生は、こまかい所に気をつけてくださるので、ありがたい。」
といった、あのコトバも思い出されてくる。
三組の先生、高橋ミヤさんは、用意してあったほうきで、子どもと一しょに、マットの上をはいている。
どこのだれだか知らないけれど、ほこりも土もなんのその、
「それ、いけっ!」
なんてやってる男の先生は、こまったもの。
さて、ミヤ先生は、子どものひざとあごに手ぬぐいはさませた。
なかなか、タマのようにはころがらない。ひざをひろげ、あごガクガクさせ、がたがた行くからだ。どこかの先生みたいに、
「こら、何回いえばわかるんだ。ホラ、ひざひろげちゃだめだっ!」
なんて、少しのききめもない、ドナリ声など出す必要はない。
ひざを開けば、あごをあげれば、手ぬぐいはポトと落ちてしまう。落とすまいと、子どもたち気をつけてやる。
「それ、こうやれ。」「やれ、そうしろ。」
などなど、号令一本だけで、子どもがうまく育って行くはずがない。
ただ、「復習しろ。」では、ダメなのだな。
先生がくふうして、子どもがやりやすいようにしてやる。高橋ミヤ式に学べ。
自分の組の子だけでなく
−−岸田さんに学ぶ−−
商売とはいえ、きょうも、四組の先生、岸田康子さんは、わからず屋の三年生を集め、プカプカドンドン、ピーヒャララと、やっている。
もう何日めだろう。当番おわった教室へ、一組から六組までの各クラス代表を集め、音楽の練習をつづけている。
おれだったらできそうもない。オンチだから。ただそれだけではない。自分の教室以外に、熱意がないのだ。
“三年二組”自分の組のことだけだったら、物によれば、きめられた授業以外に、何かすることができるかもわからない。
オレは、まったくまずいところがあるな、と思う。岸田康子さんが、プカドンの中で、何やかややってるとこなど見ると、つくずくそう思わされる。
あれこれの本に、よく書いてある。
−あさはかな、目先のきかぬ教師は、自分の教室だけにとじこもる。自分の組のことだけしか、シンケンに考えようとしない。学校全体が、学年全体が良くならなければその組も良くなりはしないのに……。わが子かわいさにおぼれ、自分の子のことだけしか考えぬ親の、いかに多いことか。勉強一つ考えても、その組全体に、
「よし、やろう」という空気がみなぎらねばダメだ。だらーっとした空気の教室からいく人かがスクスクとのびていく−−そんなこと、考えられるはずもないのに。
いとしのわが子を、人間としてもりっぱな知識もゆたかな子、そういう人に育てたい、と思ったら、わが子のいるクラス、そして学校、町、市、さらに国、世界へと、思いをひろげるべきであろうに−−。
「自分の組のことだけ先生」の弟子たちは、リコウになればなるほど、「手のつけられぬガリガリ主義者」になり、世の中のため、これっぽちのためにもならぬ人間として、終ってしまうにちがいない。
小沢勲よ、子どものためにも、窓あけよ。教室の窓、ガラガラあけよ。
ゆったりふくよかに
−−森田さんに学ぶ−−
六組の前を通るとき、そう思う。教室のぞいたりするとき、なおそう思わされる。
六組の教室には、いつもあたたかな風がながれている。春の風だ。
 ろう下歩いただけで、それは、わかる。はだにしみてくる。そこで、ぼくは考える。
ろう下歩いただけで、それは、わかる。はだにしみてくる。そこで、ぼくは考える。
わが二組の教室には、どんな風がながれているのかと……二組のろう下を歩く人は、どのような教室を感じて行くのだろうかと……
二組には六組にはないものがある。それはバク笑だ。57人全部が、ゲラゲラワッハハハハとやる。笑うということは、いいことだ。
が、〈どうひいきにみたところで〉笑いと正反対のことが多すぎる。
▼しかること、▼しかりつけること、
▼ドナリつけること、が、多すぎる。
ああ、あのとき、しかっておいてよかったしかりつけたからこそ、あの子は、あれだけ良くなったのだ、なんてことは、長い教師生活中、たったの一度、松葉づえの友だちをいじめた子を、なぐったことその一つだけだ。
「よらば切るぞ」といった顔は、だんだんへらしていこう。六組の先生、森田信子さんのように、ゆったり、ふくよかに生きたいものである。
勤務評定のこと
−−あとがきにかえて−−
ぼくは、「学級だより」三号にわたって、同じ学年の三人の女先生から教わることを書きました。書き終って、すぐ頭へ来たことは、もし勤務評定がやられるようなことになったなら、なまぐさ教師のボクなど、こんなことを決して書きはしない、ということでした。
勤務評定のない、今の生麦小学校では、
・だれも、いばる者がなく
・だれも、ちぢこまる者はなく
・だれも、けっこう楽しく
・おたがいに、じょう談など言いあい、
・各学年とも、週に一度はかならず、今川やきかラーメンなんか食べながら、子どものこと、自分の子どものこと、商売をはなれたウンとくだけた話にいたるまで、暗くなるまでやってます。
「こんなこと、決して書きはしない」といったのは、三人の点があがれば、自分の点がさがるようになっているからです。
ボクなど、校長に、なかまのつげ口にでも行くようになるかわからない。
・明かるい学校で育つ子は、明かるい。
・夫婦円満な家庭に育つ子は、明かるい。
▼暗い学校に育つ子は、暗い。
▼校長−−教師、教師−−教師の間がらの、円満でない学校で育つ子は、暗くなるに決まっている。
生麦小学校よ。子どもたちのために、今のままであれ、今のまま明かるい学校であれ。
〈神奈川方式ヒックリ返サレタ夜〉イサオ
11
課題されてから、大変ケンキョな先生になった。でも、ほとぼりがさめれば、これを書きおえて七十五日もすれば、また、もとのもくあみ先生にもどりそうだ。小沢いさおの歴史をふり返ってみれば、どうもそうなる可能性がつよい。神奈川に、勤務評定がやられるようになれば、その可能性というヤツ、うんと色こくなりそうだ。
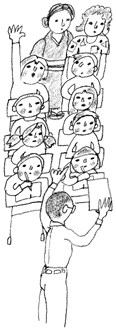 だが、サルまねにしたって、とにかく、伝統に輝く、生活綴方的教師の、そのまねだ。だから、せい一ぱいまねしているホーシュウとして、オレの分にすぎた物をもらっている。子どもの手紙を毎日ポケットにあっためている。
だが、サルまねにしたって、とにかく、伝統に輝く、生活綴方的教師の、そのまねだ。だから、せい一ぱいまねしているホーシュウとして、オレの分にすぎた物をもらっている。子どもの手紙を毎日ポケットにあっためている。
こういう物を、いっぱいもらえる教師で、いつもいたい。メッキがはげかかったら、化けの皮が見えそうになったら、こういう物を心こめて読ませてもらおう。わたしの「教育勅語」そして、わたしの最良の「勤務評定」。
★ 巴 ゆかり
先生は、どうして、おかあさまがたがくると、みんなをおこらないの。
わたしは、どうしてかしりませんが、すこしわかっています。
先生は、みんなをおこったところを、みせたくないんだと、わたしはおもいます。
先生は、はずかしがりやだから、みせたくないんだとおもいます。
だって、先生は、おかあさまのところでは、いっかいもおこったことはありませんから。
★ 孝一の母
授業中の先生のお話の中で枝話(ダッセンのこと−−小沢)が多いと思うので、子供達が、その方にひっぱられて、かんじんの質問事項を忘れてしまうのではないかと思います。
|